提供開始の時点では利幅のあった商品やサービスが、しばらく経つと値下げが始まるのはよくあることです。

車のアクセルペダルをずっと同じ位置まで踏んだままだと、なぜかスピードは減速します。
ときどき踏み増しては戻す、ということを繰り返さないと一定速度は保てません。
仕事もそれと同じで、同じことを繰り返す仕事の価値は、よほど特殊なもの以外はだんだん価値が下がって見られてしまい、自然とコストダウンの波に飲み込まれます。
そうして利益は減衰してくる。
ライバルが強い場合はなおさらです。
そして、薄まった利幅の中で、業務だけは増大・複雑化してくるのが成熟期。
この時期のビジネスでは、末端の労働者環境がブラックになりやすい。
ブラックを生まないビジネスモデルとは
成熟期を迎える時点までに新たなビジネスモデルを生み出す力が無い場合、利益を出すために弾力性のある人件費にしわ寄せが行きがちになる。
賃金が直接カットされることもあるし、スキルが上がったのに見返りが無いなどの間接的なカットもある。

そして、納得のいかない処遇のまま激しくこき使われるという身体と精神へのダメージが、最もひどいしわ寄せの形ではないでしょうか。
価格硬直化を押し付けるな
コンビニ加盟店は、資金と労働力の提供者です。
本部にそれらを差し出して、その見返りとして利益を得るスタイルの事業者と言えるでしょう。
販売する商品やサービスが値下げ合戦に飲まれて利幅を失うのとは、ちょっと趣が違う。
セブンイレブンの”改良”は何かと悪評が高いですが、消費者側の不満の声は「値上げしてるのに、量は減ってる」なので、販売価格が下がっているわけではないと言えるでしょう。
(私のお気に入り「ヒロシの時事ニュースチャンネル」より)
メーカーが価格を下げて卸さないといけなくなるといった意味での「利幅減少」は、コンビニの加盟店には当てはまりません。
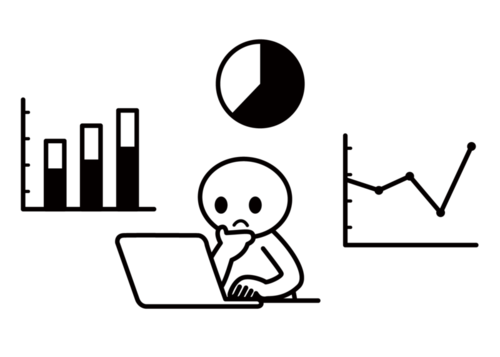
本部の側では色々なコストダウンの渦が巻いているのですが、それは加盟店と共有するタイプの苦しさではなく、本部の施策がねじ曲がった形で起きている加盟店舗での問題は、本部ではリアリティが無いと言って過言ではない気がします。
こうなると、一枚岩とは到底言い難い。
『加盟店』は”代理店”や”販売店”より重荷になってしまった
ところで、「代理店」という言葉があります。
一方「販売店」という形態もあります。
こちらの図がわかり易かったので紹介します。
「業務提携・契約ドットコム マスター行政書士事務所」という事業者の方のサイトです。(ちなみに代表者の方のプロフィールを見たところ、「日本メンタルヘルス協会」でカウンセリングを学んだ方で、私と同窓でした)
これによると・・
「販売店」は販売店契約に基づき、売主から買った商品を顧客に再販する形態
「代理店」は代理店契約に基づき、顧客に斡旋や仲介をし、販売自体は売主が行う形態
販売店の場合、顧客に売れた時に利益が得られ、売れなかったら仕入れた分が損になるのでコンビニに似ていますが、顧客への売価は販売店が決められるなどの自由度があります。
コンビニは、加盟店が本部から商品を仕入れ、決められた価格で販売しなければならない
さらにコンビニの場合、フランチャイズシステムによって顧客へ売りやすくなり、利益が上げやすくなる代償として、本部へのロイヤリティー支払いも発生します。
本部の利益が乗った価格で仕入れたうえに、売上に応じたロイヤリティーも支払うため、見た目以上に資金負担は大きい。
充分に潤うだけの利益が無ければ、事業成功のハードルはかなり高めになります。
加盟店が文句を言えない時代は、とっくに終わっている
平成初めごろの成長期までにコンビニのフランチャイズへ加盟した店舗の場合、かなり分の厚い「商いの手ごたえ」まで得られるケースが多かったので、当時ならば高いハードルなのもやむなしと言えたでしょう。
令和の現在でも、恵まれた立地などの後押しによって業績のよい店舗であれば、フランチャイズの恩恵を厚めに受けられる。
しかし、本部の誇る整ったシステムをもってしても、それを上回る現場の苦境との差し引きで、明らかにマイナスだなと加盟店に思わせるほどの状況になったとしたら、むしろ「自由度の低い販売店」と言ったほうがよいかもしれません。
販売店や代理店には自由度がある
販売代理店の募集サイトでは「副業でも稼げる」といった宣伝文句が見られることがあり、「他の仕事をしていても良い」ということになります。
また、「既存顧客とのつながりを使って販売実績を上げてもらいたい」なども、売主が販売店の営む本業を尊重しているからこその宣伝文句でしょう。
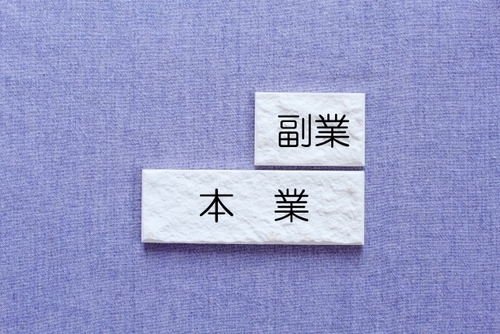
売主に一挙手一投足まで束縛されない商売
副業で稼げることを標榜する販売店募集サイトの存在から、「代理店」とか「販売店」の中には、”本業のかたわら”で行っている事業者が確実にいることが分かります。
さすがに競合他社の製品やサービスを掛け持ちで契約をすることはできないにしても、「その会社の商品しか扱えない」「事業場を他の仕事の営業活動に利用できない」といった制約は無いはずで、むしろ自社の看板の脇などに『〇〇代理店』などと記し、あくまでもメインは自社の事業として自由に動ける場合が多いと思います。
フランチャイズが「販売代理店」と比べられるようになったら終わり
フランチャイズのビジネスモデルが弱く、加盟店が充分な収益を上げ得ない中で、”販路”扱いされるのは非常につらい話です。
「仕入れたのなら、そこから先はお宅の裁量で責任もって売らないと、そちらが損するけどそこは自己責任でよろしく」
と本部に突き放され、助けを求めてもスーパーバイザーからは「助言」というより「ダメ出し」が主になる。
業績の良くない店舗は、このスパイラルに落ち込みやすくなるでしょうから、そうなるとシステムが整っているほど自由度が狭まった『不自由な販売店』と言わざるを得ないとしか言いようが無くなってきます。
当然のことですが、フランチャイズは優れたシステムを持っていますから、販売店や代理店とは一線を画する矜持があるはずです。
だからこそ、加盟店を豊かにすることだけには、どうしてもこだわりを持つ必要があるはずです。







